仮想通貨はインターネット上でやり取りできるデジタル資産ですが、管理方法によって大きく安全性や利便性が変わってきます。
特に、仮想通貨の仕組みを初めて知ったばかりの方の中には、「取引所に資産を置くだけで大丈夫なのか」「もっと便利な管理方法はないのか」と悩まれる方も多いかもしれません。
そこで本記事では、タブレットやApple Watchなどのデバイスを活用した仮想通貨の管理方法について詳しく解説いたします。
例えば、おすすめのイーサリアムウォレットを使えば、より安全に資産を管理することができます。
ただ、まずは日常的に活用しやすいデバイスで資産を安全に管理する方法を知っておくことが大切です。
仮想通貨の管理にデバイスが必要な理由
仮想通貨は実体のないデジタル資産だからこそ、専用の管理体制を整える必要があります。
いわゆる現金やカードとは異なり、ネットワークを通じてアクセスすれば世界中のどこからでも送受信できるのが特長ですが、その一方でパスワードの流出やフィッシング詐欺といったセキュリティリスクも存在します。
仮想通貨を安全に保管するためには、ウォレットと呼ばれるシステムを利用することが一般的です。
ウォレットには主に「ホットウォレット」と「コールドウォレット」の2種類があります。ホットウォレットとは、インターネットに常時接続された状態で利用するタイプです。
スマホやパソコンのアプリで管理するため、素早く送受信できる反面、ネット接続が前提なので不正アクセスを受けやすいというデメリットがあります。
これに対しコールドウォレットは、USB型のハードウェアウォレットなど、オフライン状態で管理する手法です。
ハッキングリスクが低い反面、紛失すると復旧が難しくなる点は注意が必要といえます。
デバイスを活用すれば、これらのウォレットのセキュリティをより強化したり、運用を便利にしたりできます。
パスワード管理を指紋認証や顔認証と組み合わせたり、OSのアップデートによるセキュリティパッチの適用でリスクを低減が可能です。
タブレットはスマホより画面が大きく、パソコンより持ち運びしやすいので、仮想通貨の管理にちょうど良いデバイスです。
仮想通貨を管理するにはウォレットアプリを使うことが多いですが、タブレットの大画面で操作するとアドレスの入力ミスや送受信の確認を丁寧に行いやすくなります。
さらに生体認証が搭載されたモデルなら、指紋認証や顔認証で瞬時にウォレットへアクセスできるため、パスワードを都度入力する手間を減らしながら安全性を保つことができます。
Apple Watchで仮想通貨を管理するメリットと限界
Apple Watchはメインというより、仮想通貨管理の補助デバイスとして活躍します。スマートウォッチには取引所やウォレットアプリの通知機能があり、価格の急変動や送金リクエストなどを手首で即座にキャッチできるのがメリットです。
たとえばCoinbaseやBinanceなどは、アプリの通知設定をオンにしておけば、価格アラートや取引完了の連絡をApple Watchで受け取ることができます。
外出中にスマホを取り出す手間を減らし、仮想通貨の動向を見逃さずに把握できるでしょう。
しかしながら、Apple Watchの画面はタブレットやスマホに比べると格段に小さく、実際の取引操作には向いていません。
文字入力がしにくいだけでなく、大画面での二段階認証なども行いにくいため、送受信の主導権はあくまでタブレットやスマホに任せるのが安全です。
ウォレット自体をApple Watchで管理できるわけではなく、あくまで「通知の確認や認証の確認画面の補助」程度に留まるのが実情といえます。
デバイス選びのポイントと注意点
仮想通貨の管理に使うデバイスを選ぶ際は、セキュリティと利便性のバランスをどこに置くかが重要です。
たとえば専用のハードウェアウォレットはオフラインで保管するコールドウォレットとしての安全性が高いものの、手軽に残高確認や取引を行うには向いていない面があります。
日常で使い慣れたタブレットやスマホであればアクセスしやすい一方、ネット接続が前提となるのでウイルスやハッキングへの警戒が必要です。
デバイスを選ぶ際は以下の点を意識すると良いでしょう。
まずはOSやセキュリティアップデートが継続的に提供されるものを選ぶことです。
最新のソフトウェアでは既知の脆弱性が修正されている可能性が高いため、定期的なアップデートが行われる端末が望ましいといえます。
また、耐久性やバッテリー持ちも考慮すべきポイントです。外出先で頻繁に確認を行うなら、充電切れが起こりにくいモデルを選ぶと安心です。
専用端末としてタブレットを1台用意して仮想通貨に特化させる人もいれば、普段使いのスマホやパソコンと共用している人もいます。
専用端末は余計なアプリを入れずに済むためセキュリティ的に好都合ですが、コストがかかる点や持ち歩きの手間が増える点が気になるかもしれません。
一方、日常デバイスとの共用はコストを抑えられますが、普段使うアプリやウェブサイトの影響を受けやすいこともあり、慎重な対策が求められます。
また、パスワードの使い回しは最も危険なので、必ずデバイスごとに異なる複雑なものを設定してください。
パスワード管理ツールやメモ帳などに保管する場合は、不正アクセスされない工夫が大切です。総合的に見て「安全」と「便利」のバランスをどこで取るかが、デバイス選びのカギといえるでしょう。
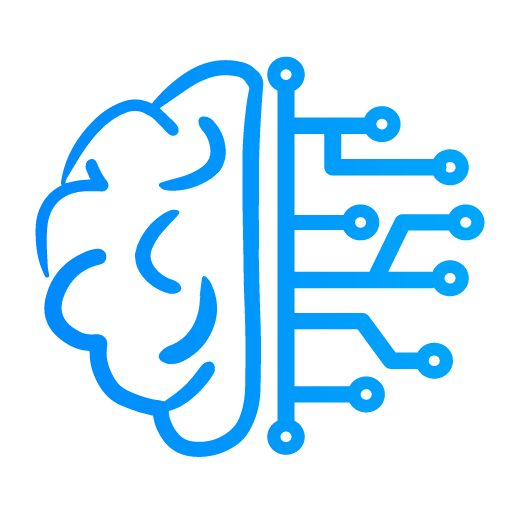



Comments